新型コロナウイルスの流行以降、リモートワークの普及などにより、働き方は大きく変わってきました。
その中で、「ジョブ型雇用」と呼ばれる働き方が注目を集めています。
加えて、今までの雇用スタイルを指す「メンバーシップ型雇用」という言葉も
耳にするようになってきていませんか?
そのため、「ジョブ型とメンバーシップ型って何が違うの?」や
「それぞれのメリット・デメリットには何?」と思っている人も少なくないでしょう。
今回は、これらの疑問の解消の助けになる話をしていきますね。
ジョブ型雇用とは

まずは「ジョブ型雇用」とは何ぞや? というところを見ていきましょう。
ジョブ型雇用とは、欧米で主流となっている働き方※です。
(※北米は「新卒採用が少なく、中途採用がメイン」、
「ヨーロッパ(ドイツ)では新卒採用が多い」など、国や地域によって差異がある)
「あらかじめ企業側が定めた職務内容(ジョブ)に基づき必要な人材を採用する制度」で、労働者は「明確なジョブディスクリプション(内容を詳細に記した職務経歴書)の情報」を元に、業務内容や責任の範囲、必要なスキル、勤務時間、勤務場所などを詳細に擦り合わせた上で雇用契約を結びます。
つまり、「実際の仕事内容に合わせた働き方」であり、企業にとっては
「専門職を採用をしたい場合に有効」な雇用方法と言えるでしょう。
なお、このジョブ型雇用が注目されるようになった背景には、
2018年から2019年にかけて、経団連(日本経済団体連合会:日本経済を担う大企業などが
集まって作った組織)の第5代会長である
中西宏明氏が「日本における従来型の雇用手法は限界である」という主張をしたことも関係しています。
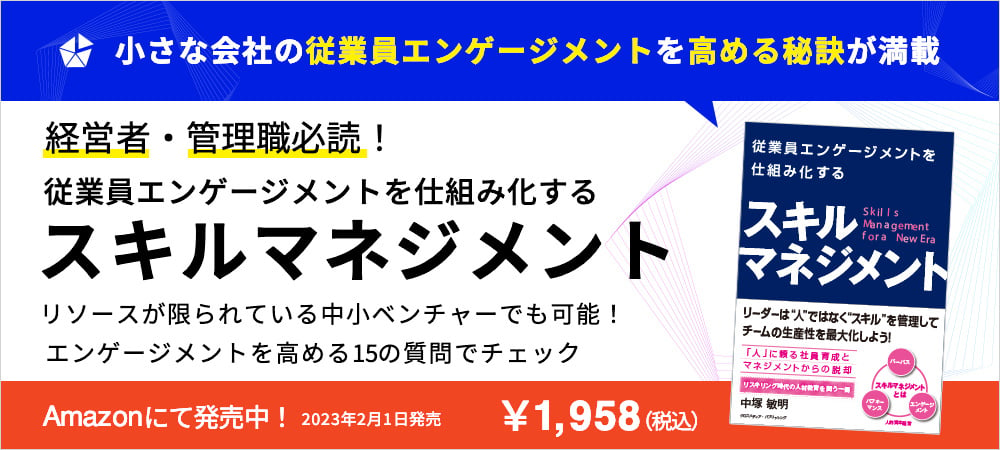
従業員エンゲージメントを仕組み化する スキルマネジメント:中塚敏明著
メンバーシップ雇用とは

では、「日本における従来型の雇用手法」とは何なのでしょうか?
もっとも分かりやすいイメージとしては、「【新卒一括採用】で【年功序列】のある【終身雇用】」でしょう。
この働き方では、新卒入社した労働者は、「総合職として就職し、企業側による適性や
潜在能力を見込まれた配置をされ、配置転換あるいは転勤などを通じて、
企業活動に必要なスキルを備えた人材に成長」していきます。
こうした働き方は、「仕事をするために働く」のではなく、「働くために企業の仲間になる」
ことから、「メンバーシップ型」雇用と呼ばれます。
ジョブ型雇用のメリット・デメリット

では、ジョブ型雇用にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
働く側と雇う側とでは、それぞれの利点や不利点が異なるため、「労働者」と「企業」それぞれに分けてみていきますね。
労働者
メリット
・スキルを磨きやすい
・自分の得意分野や学びたい分野に集中できる
・成果を上げやすい
・リモートワークと相性が良い
・仕事をするだけでスキルアップにつなげられる
・成果に応じて給与が決まることから、モチベーション向上にもつながる
デメリット
・スキルの自己研鑽(けんさん)が常に必要
・携わる業務がなくなった場合、失職のリスクがある
企業

メリット
・即戦力を採用できる
・専門性のある人材を確保・育成できる
・生産性の向上・業務効率化に有効
・業務成果に応じた社員の正当評価が可能
・職務が処遇と連動することで、年功型処遇が解消されやすい
・従業員一人ひとりの役割を明確にできる
デメリット
・より好条件の会社に転職されやすいことから人材流出などのリスクがある
・企業側の都合による転勤や配置転換、柔軟な職務の追加などが難しい
・ジェネラリスト(何でも屋)としての育成が難しい
・人材が見つかりにくい
・帰属意識が低くなりやすい
・チームワークが醸成されにくい
・職務定義書のメンテナンスなどに運用コストがかかる
労働者・企業を問わず、メリットもデメリットも「専門分化されていること」に理由があると言えそうですね。
「専門的な知識やスキルを持つ人材」が働く上では「うってつけ」
であることは「間違いない」と言えますが、同時に「諸刃の剣であること」も心に留めておくべきでしょう。
メンバーシップ型雇用のメリット・デメリット

では、旧来からの働き方である「メンバーシップ型雇用」には、
どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
こちらも「労働者」と「企業」に分けて見ていきますね。
労働者
メリット
・ジョブ型雇用よりも安定した雇用を得られる
・勤続年数が長くなることで昇給や退職金額の増額などがされる
・自分に合う仕事を見つけられる可能性がある
・初めて取り組む仕事であっても研修などを受けられるため覚えやすい
デメリット
・勤続年数や任されている仕事の範囲などによる差が出やすい
・全く希望しない部署に配属される可能性がある
・会社都合による配置転換や転勤がある
・仮に高度な知識や有能なスキルを持っていたとしても無視される可能性がある
・前提条件であったはずの年功序列や終身雇用などの考え方自体が既に揺らいでいる
企業

メリット
・強化したい分野への人材異動などが比較的簡単にできる
・長期的な視野で教育できる
デメリット
・専門職の人材が不足しやすい
労働者にとっては「安定した雇用を得られる」一方、「会社の一存に振り回されやすい」、企業にとっては「扱いやすい人材を手に入れられる」一方、「専門性に欠けやすい」と言えそうですね。
ジョブ型雇用が「急速に存在感を増している」と言っても、
現状ではメンバーシップ型雇用は「まだまだ一般的」と言えます。
そのため、この先は「メンバーシップ型からジョブ型に切り替える企業が増えてくる」かもしれませんね。
まとめ

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説してきました。
対になる考え方ではありますが、基本的に優劣はありません。
会社の規模や事業内容などにより、どちらを採用していくかは
ケース・バイ・ケースで変わっていくと言えるでしょう。
あなたの会社にあった採用方式を取ることで、従業員とのミスマッチを未然に防いで、
幸せな雇用関係を築いていけると良いですね。
